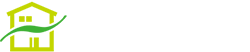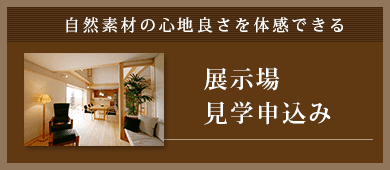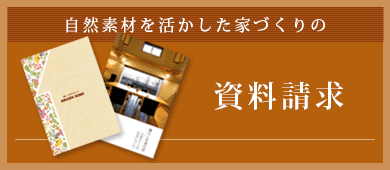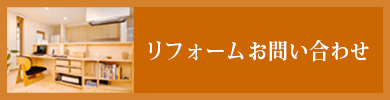三徳山投入堂(国宝)と三朝温泉を訪ねて
― 自然と人の営みが重なる場所 ―
先日、以前から親交のある鳥取県倉吉市にある工務店さんの創立50周年式典参加に伴い三徳山投入堂(なげいれどう)と、三朝温泉にある河原風呂(無料の露天風呂)を訪れてきました。どちらも以前から気になっていた場所でしたが、実際に行ってみると、自然と人の歴史が重なり合ってきた深さに圧倒されました。今回はその魅力を、歴史的な背景とともに紹介したいと思います。
■ 三徳山・投入堂 ― 「投げ入れた」ように建つ国宝
三徳山(三佛寺)は、古くから修験道の聖地として知られています。山岳信仰の祖といわれる役行者(えんのぎょうじゃ)が開いたと伝わり、険しい山道を登ることで精神を鍛える修行の場として多くの山伏が訪れてきました。
山の奥にひっそりと建つ国宝・投入堂は、まさに圧巻の一言。断崖絶壁の窪みに張り付くように建てられ、まるで天から「ポン」と投げ込まれたかのように見えます。その名の由来には、「役行者が法力で投入した」という伝説と、「修験者たちが命がけで材木を運び上げ、釘を使わずに組み上げた」という説があり、どちらにしても人と自然の壮絶な関係を感じさせます。

朝霧の晴れ間に現れた全貌
岩肌の形をそのまま生かしながら建物が据えられており、現代の建築基準では考えられない大胆な造りです。自然を読み解き、その地形に合わせて建物を馴染ませていく姿勢は、現代の木造建築にも通じるものがあります。
■ 三朝温泉 ― “三つの朝”で癒える湯治の湯
三徳山から車で10分程の場所にあるのが、三朝温泉(みささおんせん)です。その歴史は古く、平安末期〜鎌倉時代に発見されたともいわれます。「三朝」という名前の由来は、“三つの朝 湯に浸かれば病が治る”という言い伝えに基づいています。
三朝温泉は世界的にも珍しい高濃度のラドン泉で、微量の放射線が体の自然治癒力を高める「ホルミシス効果」があると言われ、昔から湯治場として人々に愛されてきました。温泉街を歩いているだけで、どこからともなく湯けむりが立ち上り、歴史ある温泉地ならではの空気を感じます。
■ 河原風呂 ― 川の恵みをそのまま味わう露天風呂
三朝温泉の象徴とも言えるのが、三徳川に架かる三朝橋の河原にある無料の露天風呂「河原風呂」です。川のほとりから自然に湧き出すお湯を、地域の人も旅人も自由に使えるようにしてきた、昔ながらの共同湯文化が今も残る場所です。


かつては川の砂利を掘るとお湯が湧き出し、石で囲って簡易の浴槽を作ったのが始まりです。川と温泉と生活が一体となった、まさに「自然の恵みをそのままいただく」入浴文化。私は夜に入浴しましたが、星空と川のせせらぎと湯気だけが静かに漂い、時間がゆっくり流れていくような感覚になります。

夜の方が安心して入れます
■ 自然とともに生きる日本人の知恵
三徳山投入堂のように地形を読み、自然の中に建物を溶け込ませる姿勢。三朝温泉のように自然の湯を生活に取り入れてきた文化。
これは住宅づくりにも通じる考え方です。
・地形、風、日当たり、季節の移り変わりを読むこと
・自然エネルギーを上手に活かすこと
・その土地に合った素材や工法を選ぶこと
投入堂の木組みや、河原風呂の開放的な文化は、現代の家づくりにもヒントがあると感じました。三徳山投入堂と三朝温泉は、ただの観光地ではなく、「自然 × 人 × 歴史」が濃縮された特別な場所。実際に訪れた時の空気感や景色は、文章では伝え切れない魅力がありました。
塩毛康弐