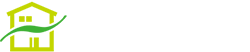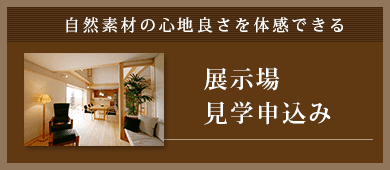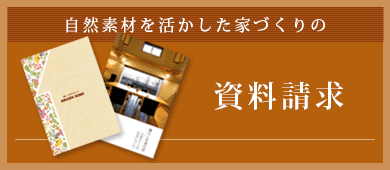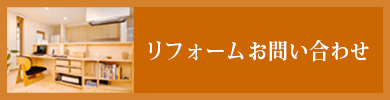住宅リフォームの減税制度とは?対象となる工事や利用方法について解説

皆さんは住宅をリノベーションすると様々な減税措置を利用できることを知っていますか?サラリーマンの方など通常なら確定申告が不要な方も、申告をすればいくつかの税金が減額されます。一般的に知られているのは所得税控除についてですが、実はそれ以外にもいくつか減税制度があります。そこで、今回は住宅をリノベーションした際に利用できる減税制度やその利用方法について紹介します。ご自宅をリノベーションするにはまとまった費用がかかりますが、減税制度を利用してお得に住まいをリノベーションしましょう。
・申請書類の一部は建築士や特定機関でないと発行できないものもあるため、建築士が在籍している工事会社に相談するのがおすすめ
目次
どんな工事が減税対象になる?

リフォームといっても全ての工事が減税制度の対象になる訳ではありません。この制度の趣旨は、「既存住宅の品質向上」であり個人の趣味趣向のための工事をサポートするためではないからです。ここでは減税制度を利用できる対象の工事を紹介します。リノベーションを検討する際は、どの工事が対象になるか事前に確認しておきましょう。
耐震工事
既存住宅の耐震基準を現行のものと適合させるための工事が対象となります。現行の耐震基準は一般的に「新耐震基準」と呼ばれており、昭和56年に改正された基準を指します。逆に、改正前の基準は「旧耐震基準」であり、減税措置の対象となるのは現状が「旧耐震基準」の建物のみです。つまり、比較的築年数の浅い住宅の耐震補強をしたとしても、減税対象とはならないので注意しましょう。
バリアフリー工事
高齢者や障害者が住むために住宅改修をする場合も減税制度が利用できます。ただし、対象となる工事内容は限られています。
- 通路等の拡幅
例:廊下を車椅子に乗る方や介助が必要な方が通れるように幅を広くする工事等 - 階段の勾配の緩和
例:住宅内の階段の段差を低くするための架け替え工事等 - 浴室改良
例:断熱性がひくく段差の多い在来浴室からユニットバスへの取り替え工事等 - 便所改良
例:和式便器から洋式便器への取り替え工事等 - 手すりの取り付け
例:屋内外各所への手すり取り付け工事 - 段差の解消
例:玄関のスロープ設置工事等 - 出入口戸の改良
例:開き戸から引き戸への取り替え工事等 - 滑りにくい床材料への取り替え
例:玄関土間の滑り止め付きタイル貼り工事等
省エネ工事
断熱工事や太陽光発電システムなどの自然エネルギー利用リフォームなどの環境に配慮した工事をした場合も減税対象となります。具体的な工事内容は以下の通りです。
- 全ての居室の全ての窓の断熱工事
例:断熱サッシへの取り替え工事 - 床・天井・壁の断熱工事階段の勾配の緩和
例:断熱材の追加・交換工事等 - 太陽光発電設備設置工事
例:ソーラーパネルおよび蓄電池の設置工事等 - 高効率空調機設置工事・高効率給湯器設置工事・太陽熱利用システム設置工事
例:エコジョーズやエコキュートへの取り替え工事等
同居対応工事
多世代が同居するために必要な設備を設ける工事が対象です。ただし、あくまで「増設」工事が対象となるため、既存設備の改修は対象外なので気をつけましょう。
- 調理室の増設
例:居室へのミニキッチン設置工事等 - 浴室の増設
例:シャワーブースの追加工事等 - 便所の増設
- 玄関の増設
長期優良住宅化工事
既存住宅の耐久性を高めて、長期間に渡り住み続けられるような住宅にすることを「長期優良住宅化」と言います。具体的には、下記のような工事が対象となります。
- 小屋裏の換気性を高める工事
例:屋根への換気棟設置工事 - 小屋裏点検口・床下点検口を取り付ける工事
- 外壁を通気構造等とする工事
例:外壁通気工法等 - 浴室・脱衣室の防水性を高める工事
例:ユニットバスへの取り替え工事等 - 家の土台・外壁の軸組の防腐工事
- 家の土台・外壁の軸組や地盤の防蟻工事
- 床下の防湿性を高める工事
例:床下のコンクリート打設等 - 雨どいを軒または外壁に取り付ける工事
- 給水管・給湯管・排水管の維持管理や交換の容易性を高める工事
例:配管の取り替えおよび点検口の設置工事等
その他のリフォーム工事は対象外?
「バリアフリーや耐震以外の工事ば対象外なの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、所得税控除についてはリフォームローンを利用している場合に限り、それ以外の工事も対象となります。例えば、下記の工事も他の要件を満たしていれば対象内です。
- 外壁・屋根の塗装工事
- トイレやシステムキッチンなど設備機器交換工事単体
- 壁クロス・床シートの張替え工事単体
- 玄関ポーチ改修などのエクステリア工事
一般社団法人 住宅リフォーム促進協議会住宅|リフォームの減税制度 よくあるご質問 Q&A
住宅リフォームで減税される税金は?

近年、住宅のリフォーム市場は年々拡大傾向にあり国や地方自治体も推奨しているため、様々な支援制度が設けられています。その中でも減税制度は適応条件が少なく、比較的どなたでも利用できる便利な制度です。ここでは、住宅リフォーム時に利用できる主な減税措置について解説します。
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会|住宅リフォームの支援制度
所得税控除
所得税とは、1月1日から12月31日までの間に得た所得にかかる税金です。先ほど紹介した対象となるリフォーム工事を行なった場合、確定申告をすると控除が受けられます。主な控除は下の3つです。
〈投資型減税〉
(リフォームローン利用の有無にかかわらず控除が受けられます。)
- 控除期間
リフォーム工事を行なった日を含む1年間 - 最大控除額
20万円(バリアリフォーム)
25万円(耐震・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォーム)
35万円(省エネリフォームと同時に太陽光発電設備設置工事をした場合)
50万円(耐震・省エネリフォームと同時に長期優良住宅化リフォームをした場合)
〈ローン型減税〉
(リフォームローンの返済期間が5年以上の場合)
- 控除期間
リフォーム後に住み始めてた年から5年間 - 最大控除額
62.5万円(12.5万円/年×5)
〈住宅ローン減税〉
(リフォームローンの返済期間が10年以上の場合)
- 控除期間
リフォーム後に住み始めてた年から最長13年間 - 最大控除額
480万円(その年のローン残高が4000万円以上の場合)
ローンを利用していないと所得税控除が受けられないと考えている方も多いかもしれませんが、投資型減税制度では100%自己資金でも利用可能です。ですから、いつもは年末調整をして確定申告をしていない方もローンの有無に関わらず確定申告をすることをおすすめします。
固定資産税減額
固定資産税とは、所有している土地や建物にかかる税金で、こちらも対象となるリフォーム工事を行なった場合には市町村に申告すれば減額制度を利用できます。ただし、行なった工事内容によって控除割合が異なりますので、事前にチェックしておきましょう。また、申告期限は工事完了後3ヶ月以内とされているため、注意してください。また、対象となる資産には上限面積が設けられています。
- 減税期間
リフォーム工事完了の翌年1年間分 - 減額割合
固定資産の1/2(耐震リフォーム)
固定資産の1/3(バリアフリーリフォーム・省エネリフォーム)
固定資産の2/3(長期優良化リフォーム)
贈与税の一部非課税
贈与税とは、個人が受け取った現金などに対してかかる税金で、満20歳以上の人が家族から住宅取得資金(新築、取得または増改築等のための資金)をもらった場合においては、上限額までの贈与について贈与税が非課税になります。こちらについても対象となるリフォーム工事を行い、尚且つ工事費用の総額が100万円以上でないと非課税対象になりません。
- 最大非課税枠
1500万円(「質の高い住宅」と認定された場合)
ポイントは「質の高い住宅」と認められた場合は非課税枠が500万円加算されるという点です。
「質の高い住宅」(増改築等)の基準に適合させるための修繕または模様替(非課税枠の500万円加算の対象)
引用元:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会|住宅リフォームの支援制度
① 断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物の住宅
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅
つまり、性能のいい住宅にするためのリフォームを行なった場合は、さらに贈与税が免除されるいうことです。
不動産取得税の軽減
不動産取得税とは、不動産を取得した際にかかる税金で、中古住宅を購入した際に合わせてリフォーム工事を行なった場合に軽減措置が利用できます。この制度の趣旨は、耐震基準に適合しない中古住宅を耐震改修するための費用を補助する目的があるため、住宅に関しては建築士などが発行する耐震基準適合証明書が必要となり、対象となる要件が複数あるため、利用できるかどうかは不動産仲介業者や施工会社へ事前に確認しましょう。
- 最大控除額
420万円(築年月日が昭和56年7月1日~昭和56年12月31日の住宅の場合)
45,000円(土地の場合)
リフォーム減税制度の利用方法や注意点は?

では、実際に各種リフォーム減税制度を利用するにはどのようにしたらよいのでしょうか?まず、利用する前に注意する点は以下の3つです。
- どの減税制度が利用できるかを事前に確認する。
- 制度によっては申告期間が限られているものもあるため、スケジュールを確認する。
- 制度によっては申告先や必要書類が異なるため、早めにリストアップする。
また、減税となる税金によって担当先が異なりますので、注意しましょう。
所得税控除及び贈与税一部非課税(国税):地域を管轄する担当税務署
不動産取得税及び固定資産税の減額(地方税):物件所在地の都道府県・市区町村の税務課
では、リフォーム減税制度を利用する際の流れを紹介します。
工事前
- 施工会社と打ち合わせをして、工事図面や工事見積書を作成してもらう。
- 資金計画を立てて、必要に応じてローン審査を依頼する。
- 減税制度が利用できるか確認する。
- 工事内容及びスケージュールが要件と合っているかを税務署・税務課や施工会社と確認する。
↓
工事請負契約締結
(ローン申込み)
- 申請には見積書や仕様書などの設計図書、契約書や各領収書のコピーが必要になるため、必ず保管しておく。
↓
工事期間中
- 申告期間が限られているものもあるため、工事期間中から準備できる資料は作成し始める。
- 書類によっては建築士に作成を依頼しなくてはいけないものもあるため、早めに相談しておく。
↓
完工・引渡し後
- 必要書類を揃えて、管轄の税務署か都道府県・市町村に提出する。
このように、工事が終わってから申請の準備をしては申告期限に間に合わない場合もあり、工事前から準備を進めておかなくてはいけません。また、施工会社が書類を作成する場合は、時間がかかる可能性もあります。スケジュールは余裕を持て組みましょう。
建築士のいる建築会社に依頼するのがおすすめ

確認申請が必要なフルリノベーション以外の部分的な改修工事は、建築士の在籍していない施工会社でも対応できます。しかし、住宅リフォーム減税制度を利用しようと考えている場合は、会社選びに注意しましょう。その理由は、申請に必要な「増改築等工事証明書」は建築士(または指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人)でしか発行できないためです。ですから、制度を利用しようとしている方は建築士の在籍している施工会社に依頼するのがおすすめです。
私たち日建ホームには、一級建築士・二級建築士が在籍しており申請に必要な書類の作成発行がスムーズに行えます。また、その他耐震やデザインに特化した有資格者が多数在籍しているため、様々な視点からお客様のリノベーションをお手伝いできます。ぜひ、リノベーションの会社選びに迷ったら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ|減税制度を活用してお得にリノベーションしましょう
今回は、リノベーションをする際に利用できる「住宅リフォーム減税制度」について詳しくお話ししました。既存住宅をライフスタイルに合わせてお得に変えられるため、どなたにもぜひ利用してもらいたい制度です。ただし、対象となるリフォーム工事は限られているため、的確に改修内容を提案できる知識や経験が豊富な施工会社に相談しましょう。私たち日建ホームでは、建築士やコーディネーターなどの専門家がが様々な角度からあなたの素敵なマイホーム作りをお手伝いします。随時相談会も開催しておりますので、興味のある方は是非ご参加ください。
千葉県でリノベーションをご検討中の方は日建ホームへご相談ください
おそらく一生に一度か二度になるであろう大切な家づくり。人生の一大事業ですので、たくさんの“希望”をお話し下さい。私たち日建ホームは「自分の家をつくるように」お客様の家づくりに真摯に取り組みます。
お約束①自分の家を建てるように心を込めて丁寧につくります。
私たち日建ホームは、千葉県我孫子市を拠点とする地域密着の工務店です。世界で唯一無二のオーダーメイドの家。暮らしの夢や希望を丁寧にヒアリングし、プロの建築技術集団として注文住宅にしかできない住み心地を実現します。
お約束②現場をきれいにします。
家は、ひとつひとつの工程を丁寧に積み重ねて出来上がっていく究極の手仕事。現場をきれいにすることでムリ・ムダ・ムラを排除しスムースに安全に家づくりができます。近隣に配慮し何よりもお施主様に喜んでいただける現場を目指します。
お約束③一生涯のパートナーとしてずっと家をお守りします。
「家」は住み始めることで「住まい」となり、住み始めてからも理想の暮らしの追求は続きます。住み続けることで変化する事柄に、ハウスドクターとして一生涯、何でも相談していただけるよう、いつも、そしてずっと傍らに居続けます。
お約束④「健康快適設計基準」で健康配慮の家をつくります。
「家」と「健康」には密接な関係があります。毎日を過ごす家のデザインや性能が身体的・精神的に大きく影響します。温熱性能(高気密・高断熱・24時間換気)、自然素材、健康配慮の家をつくります。
お約束⑤5つの保証制度で責任をもって保証します。
建設工事総合保証、無料定期点検10年間 、瑕疵担保責任10年間、地盤保証システム20年間、ぽけっと団信 住宅代金保証制度(オプション)で責任をもってお施主様の家をお守りします。
モデルハウスや展示場で家づくりを体感しよう

見学予約受付中
じっくり体感していただくために、モデルハウス見学は予約制にて承っております。見学をご希望される方は、お電話または下記ページのご予約フォームからお申し込みください。